ヒューリスティックスとは? 思い込...
14
12
ヒューリスティックスとは? 思い込みで失敗しない4つのコツ
私たちは意思決定のとき、心理学でいう「ヒューリスティックス(heuristics:発見的手法)」を用いることがあります。経験則や先入観から答えを導こうとする思考法です。
たとえば、頭髪や身長、顔立ちが「外国人風」の人を見かけたとき、「きっと英語が話せるんだろう」と考える人は多いのではないでしょうか。でも、その人は日本生まれ日本育ちで日本語しか話せないかもしれないし、外国出身だとしても英語圏とは限らないですよね。
ヒューリスティックスは便利な手法ですが、正解にたどりつきやすいわけではなく、精度が高いとはいえません。偏見や先入観による深刻な判断ミスを回避するため、私たちが無意識に使っているヒューリスティックスについて知っておきましょう。ヒューリスティックスとアルゴリズムの違いや、「代表性ヒューリスティック」などヒューリスティックスの種類について説明します。
ヒューリスティックスとは
心理学におけるヒューリスティックスとは、先入観や経験に基づく思考法。計算によって論理的に解決する手順「アルゴリズム(algorithm)」の反対です。
ヒューリスティックスの語源は、「見つけた!」を意味するギリシャ語の「Eureka」。ヒューリスティックスの定義は次のとおりです。
(引用元:ダニエル・カーネマン著,村井章子訳(2012),『ファスト&スロー あなたの意思はどのように決まるか?(上)』,早川書房.太字による強調は編集部が施した)
2002年にノーベル経済学賞を受賞した行動経済学者のダニエル・カーネマン氏と心理学者の故エイモス・トヴェルスキー氏は、ヒューリスティックスについて以下のように説明しています。
(引用元:ダニエル・カーネマン著,村井章子訳(2012),『ファスト&スロー あなたの意思はどのように決まるか?(下)』,早川書房.太字による強調は編集部が施した)
ヒューリスティックスには、メリットとデメリットの両方があるようです。どのようなものなのでしょうか? 代表的な4種類のヒューリスティックスについて見ていきましょう。
代表性ヒューリスティック
「代表性ヒューリスティック」とは、ステレオタイプ(代表的なイメージ)と比べて判断するやり方。冒頭に挙げた「外国人っぽい見た目の人は英語を話すのだろう」という推定は、代表性ヒューリスティックに該当します。
カーネマン氏とトヴェルスキー氏が発表した、代表性ヒューリスティックに関する有名な「リンダ問題」をご覧ください。皆さんなら、AとBのどちらを選びますか?
(引用元:箱田裕司・都築誉史・川畑秀明・萩原滋(2010),『認知心理学』,有斐閣.太字による強調は編集部が施した)
実験では、約90%の被験者がBを選んだそうです。しかし、Aの条件は「銀行の出納係である」の1つだけですが、Bの条件は「銀行の出納係である」「女性解放運動をしている」の2つ。Aの確率がBより低くなることは、論理的にありえないはずです。
つまり、ほとんどの人は、論理ではなく代表性ヒューリスティックを用いて判断したことになります。「銀行の出納係」と「女性解放運動家」の典型的な人物像をイメージし、そのイメージにリンダがどれだけ一致しているか、という基準で判断したのです。「偏見」ともいえるでしょう。
利用可能性ヒューリスティック
「利用可能性ヒューリスティック」とは、関連情報を広範に収集することなく、思い出しやすい・入手しやすい情報に頼って判断する方法。行動経済学の第一人者であるミシェル・バデリー教授(南オーストラリア大学選択研究所)は、利用可能性ヒューリスティックを以下のように表現しています。
(引用元:ミシェル・バデリー著,土方奈美訳(2018),『行動経済学 エッセンシャル版』,早川書房.太字による強調は編集部が施した)
バデリー教授によると、利用可能性ヒューリスティックは、スピーディーな判断を要する場面で利用されがちなのだそう。利用可能性ヒューリスティックの要因と具体例は以下のとおりです。
頻繁に接しているもの
習慣的行動や、よく目にする広告など。
個人的に関わりのあること
自分の体験や周囲に起こった出来事、生年月日など。
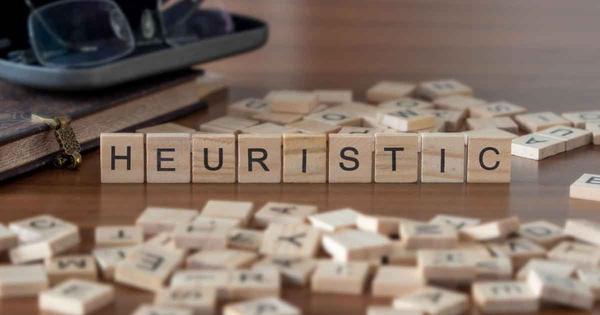
インパクトのある出来事
衝撃的なニュースなど。
具体性があるもの
友人やWebサイトの口コミ。
時間は有限。物事を判断・決定するとき、関連する全ての情報・可能性を検討するのは不可能です。
そのため、思い出しやすい・入手しやすい情報から判断する利用可能性ヒューリスティックは、理にかなっているともいえるでしょう。ただし、自分の知らない・入手しにくい情報が重要になる場合もあるため、利用可能性ヒューリスティックに頼ると、重大な情報を欠いたまま判断することになってしまいます。
係留と調整ヒューリスティック
「係留(アンカリング)と調整ヒューリスティック」とは、最初に得た情報を手がかりにして推定する方法です。アンカリングとは、船をロープでつなぎとめておくこと。海底に沈めて船を固定する「アンカー(いかり)」に由来します。
係留と調整ヒューリスティックの効果を理解するため、次の例をご覧ください。
(引用元:市川伸一(1997),『考えることの科学 推論の認知心理学への招待』,中央公論新社.太字による強調は編集部が施した)
上記2つの例では、どちらも「トルコの人口は何人か?」と聞いています。しかし、「6,000万人」「2,000万人」という数字に影響され、被験者の答えは大きく変わっていますね。
このように、事前に聞いた情報を基準にして答えを出してしまうのが、係留と調整ヒューリスティックなのです。なお、アンカーによって考えが左右されてしまうのは「アンカリング効果」と呼ばれます。
シミュレーション・ヒューリスティック
「シミュレーション・ヒューリスティック」は、経験や先入観などから架空のシナリオを思い描いて結果を推定するやり方です。
社会心理学者のスーザン・フィスク教授(プリンストン大学)とシェリー・テイラー教授(カリフォルニア大学)によると、シミュレーション・ヒューリスティックは、将来の予想・因果推論・反実仮想などに使われるそう。以下のように、架空のシナリオに基づいて推定します。
【将来の予想】
人前で話すのは苦手なのに、結婚式のスピーチを頼まれてしまった。→「学芸会で、緊張のあまりセリフを忘れてしまったことがある。今度も、頭が真っ白になってまた失敗するにちがいない」と、過去の経験から未来の失敗を予想する。
【因果推論】
デスク上に置いてあったマグカップが割れていた。→「隣のデスクに積み重なった書類が、私のデスクに倒れてきている。書類の山が崩れたせいでマグカップが床に落ち、割れてしまったのでは」と、原因と結果の関係を推定する。
【反実仮想】
自動車で空港に向かったところ、渋滞に巻き込まれ、フライトの時間に遅れてしまった。→「車ではなく電車で向かっていたら、時刻どおり空港に到着でき、飛行機に間に合ったのに……」と、事実と異なる想定をする。
上記の3つは妥当な推論に思えるかもしれませんが、あくまで「架空のシナリオ」にすぎません。たとえば、過去に失敗したからといって未来も必ず失敗するとはかぎりませんよね。それに、マグカップが割れた原因についても、割れる瞬間を目にしたわけでないのですから、やはり想像の域を出ません。また、信号機の故障や事故によって、電車が大幅に遅れることも珍しくありませんよね。正しい判断とは言い切れないのです。
以上、4種類のヒューリスティックスを紹介しました。ヒューリスティックスという言葉自体は聞き慣れないかもしれませんが、上記のような考え方には皆さんも心当たりがあるはずです。
ヒューリスティックスのデメリットを避ける方法
ヒューリスティックスには、素早く意思決定できるメリットがある一方、判断ミスを誘発するというデメリットもあります。ヒューリスティックスのデメリットを回避するには、どうすればよいのでしょうか?
『ハーバード・ビジネス・レビュー』誌に掲載された1998年の記事「意思決定における隠れた罠」によると、ヒューリスティックスの落とし穴にはまらないためには、先入観や偏見といった「バイアス」の存在を常に意識することが重要なのだそう。ヒューリスティックスの種類ごとに、バイアスを意識する方法をご紹介します。
ステレオタイプを疑う
代表性ヒューリスティックから生じるデメリットを避けるには、自分の思考が「ステレオタイプ」に影響されていないか、よく考えてみましょう。以下のように自問自答してみてください。
外国人が困っているようだ。英語で話しかけてみようかな。……でも、よく考えたら、外国人に見えるからといって外国人とはかぎらないし、外国人がみんな英語を話すわけでもない。ここは日本だし、日本語で話しかけてみよう。通じなかったら英語に切り替えればいいや。
情報収集に手間をかける
利用可能性ヒューリスティックが引き起こしかねないデメリットを避けるには、手に入りやすい情報だけに頼るのではなく、少し手間をかけて情報を集めましょう。直感的な印象で判断せず、具体的な数字を確認することが大切です。
去年インフルエンザにかかった知り合いはいない。でも、だからといって、インフルエンザの危険性が低いとはかぎらない。国立感染症研究所の「インフルエンザ流行レベルマップ」を見て、感染の拡大具合を確認してみよう。
飛行機事故の衝撃的なニュースが、連日放送されているなあ。事故は恐ろしいけれど、飛行機に乗るのは危ないのだろうか? 政府統計ポータルサイトで「交通事故の発生状況」を、運輸安全委員会のWebサイトで「航空事故の統計」を確認し、自動車事故と飛行機事故の発生確率を比べてみよう。
アンカリング効果を意識する
係留と調整ヒューリスティックのデメリットは、アンカリング効果によって引き起こされます。アンカリング効果の存在を意識し、「自分の思考は、あらかじめ提示されたほかの情報に影響される」と自覚しておきましょう。
通常価格1,000円の高級肉が、特別割引で500円か。お得だな、買おうかな? ……でも、元の価格が1,000円だと知らなければ、私はこれを買いたいと思うかな? よく考えてみよう。
小説を書いてみたいけれど、何日くらいかかるだろう。作家のA氏は、デビュー作を7日で書き上げたというから、私は2倍の14日かな? ……いや、「7日」という数字は、私とは何の関係もなかった。力量も違うし、ページ数も違う。まずはやってみて、自分のペースを知ろう。
希望的観測を捨てる
シミュレーション・ヒューリスティックから生じるデメリットを避けるには、「希望的観測」や「過去の失敗に起因する不安」を取り除く必要があります。ポジティブ思考・ネガティブ思考にとらわれず、目的達成に必要な手段をニュートラルな視点で考えましょう。
資格試験に合格できたら、嬉しいだろうなあ。合格して喜んでいる自分の姿をはっきりイメージできる。合格できそうな気がしてきた! ……いや、このイメージと、実際の合格可否は何の関係もない。冷静になって、確実に合格するための勉強計画を立てよう。
人前で話すのは苦手なのに、スピーチを頼まれてしまった。どうやって断ろう……。でも、冷静になってみると、前に失敗したことがあるからといって、次も失敗するわけではない。スピーチのやり方の本を読んで、練習してみるか。
上に挙げた自問自答の例を参考に、意思決定の際、「これはヒューリスティックではないか?」 と立ち止まって考えてみましょう。
***私たちの意思決定は、何らかのヒューリスティックスになりがち。ヒューリスティックスには、素早く判断を下せるメリットもある一方、深刻な判断ミスを引き起こす可能性もあります。失敗を防ぐため、今回ご紹介した方法をぜひ試してみてくださいね。
(参考)ダニエル・カーネマン著,村井章子訳(2012),『ファスト&スロー あなたの意思はどのように決まるか?(上・下)』,早川書房.ハーバード・ビジネス・レビュー編集部編(2019),『意思決定の教科書 ハーバード・ビジネス・レビュー 意思決定論文ベスト10』,ダイヤモンド社.箱田裕司・都築誉史・川畑秀明・萩原滋(2010),『認知心理学』,有斐閣.高野陽太郎(2013),『放送大学教材 認知心理学』,放送大学教育振興会.スーザン・フィスク著, シェリー・テイラー著 , 宮本聡介ら編訳(2013),『社会的認知研究 脳から文化まで』,北大路書房.市川伸一(1997),『考えることの科学 推論の認知心理学への招待』,中央公論新社.日本認知心理学会編(2013),『認知心理学ハンドブック』,有斐閣.ミシェル・バデリー著,土方奈美訳(2018),『行動経済学 エッセンシャル版』,早川書房.相馬正史・都築誉史(2014),「意思決定におけるバイアス矯正の研究動向」,立教大学心理学研究,Vol.56,pp.45-58.杉本崇・高野陽太郎(2011),「対象に関する知識量が少ない場合のアンカリング効果:意味的過程説と数的過程説の比較」,認知心理学研究,第8巻第2号,pp.145-151.GLOBIS 知見録|本当にその確率? -シミュレーション・ヒューリスティックGLOBIS 知見録|心をつかむプレゼンテーション10のコツとはプレジデントオンライン|なぜマックではポテトを頼んでしまうのか幻冬舎ゴールドオンライン|会社の売却・・・買い手から高く評価される「業績推移」とは?Tversky, Amos and Daniel Kahneman (1983), “Extensional versus intuitive reasoning: The conjunction fallacy in probability judgment,” Psychological Review, 90(4), pp. 293–315.
【ライタープロフィール】上川万葉法学部を卒業後、大学院でヨーロッパ近現代史を研究。ドイツ語・チェコ語の学習経験がある。司書と学芸員の資格をもち、大学図書館で10年以上勤務した。特にリサーチや書籍紹介を得意としており、勉強法や働き方にまつわる記事を多く執筆している。








