「新しいことをすれば会社も変わる...
28
07
「新しいことをすれば会社も変わる」初めてのクラウドファンディングで生まれた効果:PC広報風雲伝(第27回)
広報にまつわる人との接し方を中心に、たくさんの失敗と格別な体験を時事ネタ交えつつお伝えしていく本連載。今回は前回の続き、ものづくりが生んだ副次的効果についてお話をしたいと思います。
プロダクトを作るということは多少なりとも企業文化に影響を与えます。そういった意味ではUHKBの取組みは企業にとって新しい提案を投げかけたことになるのではないでしょうか? 広報がどこまでやるかは別の話ですが、乗り掛かった舟ではあります。
「いいな」は誰にでも言える
新しい取組みだったUHKBプロジェクト。今までと成り立ちが違うためにスタートをするのにとても多くの時間と議論を必要としましたが、そもそものスタートはただ理想を語り合う場から始まったものでした。
広報活動を行なう上で中心となるのはリリースや新商品の紹介などプッシュ型で情報を提供するものですが、もうひとつ市場の意見を採り上げるヒアリングということも重視しています。
UHKBのスタートはヒアリングから始まりました。いろいろな意見交換は目的を設定しない、いわゆる雑談。どうでもいいことから世の中の動向、噂話から個人的な話の中に同等のボリュームで”仕事“の話が出てきます。そこにはその相手の思っている本心が含まれています。
IT業界にいれば、いつぐらいにどんな部材を使ったこんな商品が出てきて、市場全体で持っている技術を考えれば、できることできないことがおおよそ見えています。「こんなものがあったらいいな」という、絞り出したような希望のメッセージに出会える可能性が雑談にあるのです。
「いいな、いいな」は誰にでも言えるのですが、それを声に出す人は少ないのです。それは簡単ではないから。そこから始まる気の遠くなるような作業がわかっていればわかっているほどに出会える確率は低くなります。
重い車輪を回そうとする人
それでも、相手の思いの強さに憧れてしまうこともあります。それはできるできないではなく、これがあれば絶対に人々が喜ぶ。お客様は絶対にこの商品を求めているという強い思いです。その強い熱い思いを実現しないで企業はほかに何をやるんだという思いにさせられます。今回のプロジェクトの根っこがここにありました。ここがスタート。この時の強い思いは、必ず成功するという強い思い込みに変わり、重い重い最初の車輪を動かす動力となりました。それは重い車輪でしたよ。簡単には回り始めない鋼鉄の車輪です。
その後の展開は社内の様々な部門との調整や、クラウドファンディングを使うことになった様々な経緯、そして、実際に作るものに対するこだわりの連続と、価格や台数などビジネスプランを作る段階での葛藤。妥協はしないと決めた以上ハードルは高くなるわけで、そこについてのたくさんの不安が付加されるなど、実務者はまるで幾重にも重なった山脈の中に取り残されたように感じたでしょう。
つらくなると「広報としてできる領域」ということを考えてしまいます。橋渡しをする仕事。それでも言い出しっぺなら動くまでが責務と感じてとにかく調整する。その大変さをすぐ脇で見ていて感じました。私もたくさんそういう経験をしてきました。チキンレースですね。途中で引き返す理由はいくらでもあり、そのボタンを押せば楽になれるという誘惑のジャッジもありました。それでも、「これが世の中に必要とされているんです」と熱く語ってくれた編集者の顔と声がどうしても停止ボタンを押させてくれない。押せないのです。
私は登山が好きなのですが、ちょっと無理なプランを立ててしまい、その行程の中でなんでこんな無理な予定を組んでしまったんだろうといつも後悔していました。実は飛行機が好きではないのに、アジア各国を短期間で回り、全く知らない航空会社のぼろぼろな機体に乗る度になんでこんなフライトスケジュールを組んでしまったんだろうと、死を覚悟するような後悔をしてきました。
それでも何故同じ事を繰り返すかというと、その先に最高の成功体験があったから。ここを超えればきっと次が見えてくる。そう思い、そしてそれを成し遂げたときに格別な思いを経験する。だからかもしれません。今回も同じ事だと思いました。なので、頑張ってほしい。
現職の広報部長もギリギリのところで社内調整を行なってきたと思います。一瞬もうだめかもという雰囲気が漂ってきましたが、そういう時はネガティブな話を避けるようにして近くに訪れる未来を見据えて乗り切ってくれたのだと思います。
そして昨年12月24日に終了したクラウドファンディング。500万円を目標にした支援額は7700万円を超えました。これは成功でしょう。しかし、これは小さな成功にすぎません。これはゴールではありません。このクラウドファンディングを活用したスキームはFCCLにクラウドファンディングを活用してもいいんだと記録を残すことになりました。今回の成果はここにあるのではと思います。
新しいことを考え、それを一から一つ一つくみ上げ、きちんと各所のネゴシエーションをし、数字を作り、プランを考え、商品化会議を乗り切る。承認されて初めてものが作れる専門の課程だけではなく、良いものを作る。お客様に評価されるものを作るという顧客目線の一点突破的な考えでもこの会社は受け入れてくれるということが、少なくとも従業員には伝えられたと思います。
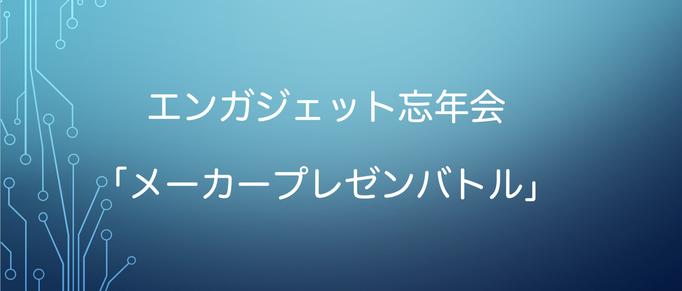
そこから生まれる新しい何か。この次はもっと楽しいことが提案されるのだろうとわくわくしています。「もっとこういうものにしたほうがいい」「全く違うコンセプトだけれど」「最近こんなものが出始めているがうちの会社でもやってみることができないか」声にならない声が聞けるような土壌が肥やされてくればそこに草木は育つ。一つのプロジェクトの成果は目に見える売り上げ数字ではなく、その後ろに控える大きな会社としての成長です。
こだわりきったものを作り出した開発者の思い、矢崎編集長のアイデアを必死に形にするべく頑張ったデザイナー、新しい売り方を認め次のプランに協力をし始めた営業部隊。そして、こういうことができるという事実を知った社員。企業を取り巻く全方位で企業価値を高める広報活動。拡げすぎて目が回る話ではありますが、あとは勝手にどんどん育っていくでしょう。そうあって欲しいです。
広報ができるのはそれらをの結果を継続的に拾い集めて報道すること、スタックしていたらフォローを忘れずにすることだと思います。成功事例を思い出すネタふりをする、厳しかった改善点を経験値で語る。その活動自体がメディアから見て面白いと思ってもらえるネタになることを信じつつ。
面白いことはたくさん副次的に生まれました。このクラウドファンディングを見て、「うち専用のものを」と独自バージョンを作りたいといってくれた企業の皆様との打ち合わせは新鮮でしたし、ありがたく思えました。これからは営業部隊の商談に移っていきますが、新しい取組みがビジネスを生む事例として活用してもらえればと思います。そして、まさにここから生まれた話としてはPFUさんとのコラボイベントが開催されたことです。
元々PFUさんは親戚関係くらいの縁がある会社です。私も現役時代はPCと一緒に周辺機器も紹介しようということで文鎮型のScanSnapをキャラバンしていました。当時のスキャナのイメージを変えた逸品だと思っています。
そんなPFUさんはHHKBというキーボードを販売されています。ストロークが深くいわゆるデスクトップPCについているようなスタイル。今回FCCLが出すUHKBはLifebookUHシリーズからキーボードだけを抜き取ったような薄型軽量のキーボード。まったく180度異なる商品でした。
そんなライバル関係にある両商品ですが、「外付けキーボード市場」という共通もあり、PRを兼ねてコラボ企画を行なうことになったのです。私自身もHHKBは名前だけ知っていましたが、実際に触ったことはありませんでした。必然的に商品を触らせて頂き、その打鍵感の良さを知ることができたことで、UHKBの打鍵感についても比較対象ができたと思いますし、今朝降り積もったばかりのような柔らかな白が特徴のキーボード、真っ黒な炭のようなキーボードと思いっきりチャレンジしているところに、まだまだ頑張らなければと思うようにもなりました。ネーミングも含めとにかく斬新です。挑戦的です。こんな商品を作ることのできる開発者とそれをよしとして商品化にGOをかけるPFUの経営陣の勘所のすごさも知るところとなりました。
自分たちが斬新な事をしていると思っていても、ほかにもこうして普通にチャンレンジしている会社があることを知るとますます挑戦をしてみたいという気持ちに駆られます。UHKBが今までになかった市場に参入することで生まれたこの企画は、矢崎編集長と両社の開発責任者がトーク形式でものづくりを語り合うということもあって、事前のやりとり含め多くのコミュニケーションを取ることとなり、とても良い企画になったと思います。
私も「バトル希望」なんて勝手に開発者を煽ったりしました。この件も同様ですがイベントがうまくいったということは当然ですが、そこで両社の広報、開発者が会話する場面、お互いの商品を深く知ることができたということが最大の成果物ではないでしょうか。具体的に今すぐに何かが起きるわけではありませんが、きっとこれをきっかけに何かが起こるかもしれません。こうして新しいものを知ること、新しい人と出会うこと、新しいことをその人たちとはじめたいと思うことが広報としての最大の収穫であったと思います。
勘違いしてはいけない周年事業
そうして2022年を迎えました。富士通PCが40周年を迎えた今年度。その集大成は期間がまもなくやってきます。広報としては面白いネタばかりでありますが、一方、社外から見て面白いと思って気にしてもらうことが一番大事な事なので、周年事業だからといって独りよがりにならないようにすることも大切です。
ここは非常に重要な広報としての論点です。以前、「うちは○○周年なんですよ、記事を書いて下さいね」と編集者に話した際、辛口のその編集者は私に「それって読者に取って関係ないですよね。何か割引モデルとかプレゼントとかあるんですか? それよりも周年の広告とか出しませんか?」とあっさりと返されたことがあります。
社内からは「今年は○○周年なんだから記事を書いてもらってきてくれ」と言われ、その上司からすると雑誌の表紙に「富士通PC○○周年!」と大きく出ることを期待していたのでしょう。でも、周年自体はお客様にも記者にも媒体にも関係ありません。周年ではなくその時に何を見せることができるかなのです。
それでも「特集もらってこい」的に会社から勢い満点で出て行った自分はどう上司に説明しようか悩みながら会社に帰った記憶があります。言い訳がほんと辛かったです。その時の辛い記憶があったので、今回の40周年においても“この時に何を見せられるか”ということが大事だと訴え続けてきました。その結果がどうなったかはお楽しみにして頂きたいと思います。先日CESでデビューしたあれです。中身については多くは触れていないので発表を楽しみにしてほしいと思います。
昨年を振り返ってみると、新型コロナウイルスの蔓延は副次的にオンライン生活を生み、飛躍的にビジネスの効率化を図ることができた時代の功罪であると思いますが、一方で人と人のつながり、例えば取材の時に生じる雑談が消えたという、マイナス面も生みました。
最近リアルで人と会うようになると、「この雑談が大切だったよね」とみんな口にするようになって、それをかみしめるように頷くというシーンがよく見られます。これからは希望的観測も含めリアルの面談も増えてくるのでは、と考えています。オミクロン株の蔓延が早くて気をもみますが、これからはリアルがあってもオンラインもなくならないと思うので、情報発信の選択肢が広がったと解釈すればとても良いことなのではないでしょうか。「2020年から一気にデジタル化が進みました。その理由はわかりますか?」って2030年くらいの教養番組でクイズのように出題されるかもしれませんね。「コロナの影響で企業の在宅勤務が進み、結果PCのオンライン利用が一気に増えた」「正解!」みたいな。
PC広報風雲伝連載一覧
秋山岳久
PC全盛期とバブル真っ只中からPC事業風雲急時代までPCメーカーで販売促進・広報と、一貫してメディア畑を歩むものの、2019年にそれまでとは全く異なるエンタテイメントの世界へと転身。「広報」と「音楽」と「アジア」をテーマに21世紀のマルコポーロ人生を満喫している。この3つのテーマ共通点は「人が全て」。夢は日本を広報する事。








